

矢田川南岸の丘陵に位置する長母寺は平安時代末期の創建である。名前のとおり母の菩提を弔うためにこの地の豪族が建立して、無住国師が再興したという寺だ。広い境内には、永い歴史にふさわしく由緒ある植物や建造物が残る寺である。
 |
|||
 |
|||
矢田川南岸の丘陵に位置する長母寺は平安時代末期の創建である。名前のとおり母の菩提を弔うためにこの地の豪族が建立して、無住国師が再興したという寺だ。広い境内には、永い歴史にふさわしく由緒ある植物や建造物が残る寺である。 |
|||
| |
|
|
|
| |
| ◇今に伝わる 貴重な文化 重要文化財 木造無住和尚座像……大正3年(1914)指定。開山堂に安置。無住国師自作とも。 無住道暁(どうぎょう)筆文書 3幅……昭和34年(1959)指定。 国登録有形文化財 本堂……濃尾地震で倒壊後、明治27年(1894)に再建 山門……18世紀後半の建築と推定されている。3間1戸の薬医門、本瓦葺 庫裡……文政11年(1828)の建築 |
 無住国師座像 (重要文化財) 『新修名古屋市史』 |
||
 山門(登録有形文化財) |
 本堂(登録有形文化財) 本堂(登録有形文化財) |
 庫裏(登録有形文化財) |
|
由緒ある植物 |
|||
|---|---|---|---|
| ◇桧葉宿木(寄生樹) 桧の葉状で10㎝位になる宿り木。 『尾張名所図会』は「すべて名僧入定の地には、かならずこれあり。紀州高野山をはじめ、其他にもありといふ」と書き、無住国師が亡くなった地なので生えているとしている。 |
 |
||
| ◇唐躑躅(つつじ) 熱田神宮の神が無住国師を尊崇して、五種の宝を寄進した。多くは散逸してしまったが、躑躅だけは江戸時代になっても残っていた。 別の伝承では、無住国師が熱田神宮を日参したので熱田の神様が喜んで躑躅を贈った。無住は熱田の神を祀る社を建てその前にその躑躅を植えたのが残ったという。 『張州年中行事鈔』に次の話が載っている。 「八重咲きの躑躅で見事な花を咲かせる。山口町に住む浪人の青山喜太夫が一本採って持ち帰り庭に植えた。1~2日後に友人が訪ねてきて驚いたが、喜太夫は神罰が下るかどうかは人次第だと言って一緒に酒を飲み始めたところ、突然顔色が変わり際限なく血を吐いた。長母寺に躑躅を返しお祈りをしたが効果がなく亡くなってしまった。その後も何人もの人が天罰を受け、最近でも3人が血を吐いて死んだ。」 『感興漫筆』の著者である細野要斎は、文久4年(1864)4月に長母寺へ行った時の様子を次のように記録している。 「無住国師影堂の前に躑躅の木あり、籬を結たり、花は既に萎む、三株あり。傍に牓(ふだ、札)を建たり、其文如左。 此八重躑躅は弘長三癸酉年 熱田皇大神宮当寺開山無住国師 塔前へ御寄附せし名木也、然に近世参詣之諸人或は一花を摘、或は一枝を折取る者神罰を蒙り、追々わびを願来る輩数多有 之故、参詣之諸人為心得記し置、可慎者也」 花や枝を採り天罰を被るものがたくさん出たので、柵で囲い立札で注意を呼びかけていたようだ。 |
|||
|
御 開 帳 |
|||
|---|---|---|---|
| ◇文化3年(1806)の開帳 『金明録』(猿猴庵日記)には、たびたび観音の御開帳が行われたことが書かれている。 筆者(猿猴庵)は参拝には行っていないようで、開帳が行われたことしか書かれていない。文化3年(1806)4月の開帳は「木ヶ崎長母寺開帳賑合。芝居・軽業等始る。」と書かれ、芝居などの興行も併せて行われ賑わったようである。 ◇嘉永2年(1849)の開帳 『感興漫筆』には、嘉永2年(1849)4月に谷汲山華厳寺の出開帳が長母寺で行われ、拝観に行ったときの様子が記録されている。 地蔵の掛け軸や曼荼羅、極楽の図などが掲示され、開山堂の両側に六地蔵や千体地蔵が安置され、夢想国師座像も拝見できた。お堂の東には歌舞伎芝居の小屋がかかり、あちらこちらに食べ物を売る店が出ていて多くの人が参拝に訪れていた。筆者(細野要斎)は、この寺はたびたび開帳をするものの訪れる人が少ないが、今回はいつもと違って非常に賑わっていると感想を述べている。 文久4年(1864)にも観音堂の御開帳に出かけているが、帳(とばり、たれぎぬ)が少し開いているだけなので見えにくいと不満を書いている。 |
|||
|
境内の風景 |
|||
|---|---|---|---|
| ◇熱田社 山門手前左に鳥居が建ち、階段を上ると小さな社がある。 ◇八十八弘法 山門を入ってすぐのところに、大きな弘法大師像と八十八弘法が安置されている。 ◇百度石 池の畔に建ち、裏面に「此水つけると いぼおちる」と刻まれている。 |
|||
| ◇石の垣根 刻まれている奉納者の名前に、歩兵三十三連隊や伊藤萬藏の文字が見られる。 なお、三十三連隊は明治30年(1897)に現在の陸上自衛隊守山駐屯地の所に本部を置いて創設され、大正14年(1925)に久居(現:三重県津市)に転営した部隊で、太平洋戦争ではレイテ島で玉砕している。 また、伊藤萬藏は垣根のほか、開山堂前の線香立てや山門前にある三十三観音の一番観音も奉納している。 |
 『大名古屋市全図』 大正13年 |
||
| ◇「関東震災惨死者供養塔」 右側に「大正十二年九月一日午前拾壱時五十八分」、左側に「死亡者九萬八千人」と刻まれ、被災から3年後の大正15年(1926)9月1日に奉納された ◇宝篋印塔 元禄9年(1696)に2代藩主光友が寄進したもの。塔の下には、光友が自ら書いた宝篋印陀羅尼と鑑真和尚が持ってきたという仏舎利が納められているという。 |
|||
 熱田社 |
 八十八弘法 |
  百度石 左:表面 右:裏面 |
|
 「歩兵三十三連隊」の文字が入った垣根 |
 「関東震災惨死者供養塔」 |
 宝篋印塔 |
|
|
|
|
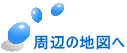  |
|